 大抵の船長や釣人の方なら潮見表(潮汐表ともいう)のお世話になっています。しかし初心者の方はもちろんベテランでも、中身そのものについてはお経の文句のように理解しがたいものでしょう。海は天体の運行に支配されています。ちょっと難しいかもしれませんが、潮のメカニズムや釣りとの関係、さらに潮見表の活用法を解説してみましょう。
大抵の船長や釣人の方なら潮見表(潮汐表ともいう)のお世話になっています。しかし初心者の方はもちろんベテランでも、中身そのものについてはお経の文句のように理解しがたいものでしょう。海は天体の運行に支配されています。ちょっと難しいかもしれませんが、潮のメカニズムや釣りとの関係、さらに潮見表の活用法を解説してみましょう。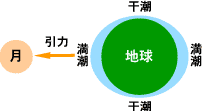 ●図をご覧になればよく分かると思います。月が一番近づいた時に、海水が月の引力により引き寄せられ、満潮(水位が最高)が起こります。直角に位置する部分は、海水が引かれるため干潮になり、その影響で反対側でも満潮現象が起こります。月は1日に地球の周りを1周しますから1日に2回/約12時間おきに潮の満ち引きが繰り返されます。これがいわゆる潮汐です。
●図をご覧になればよく分かると思います。月が一番近づいた時に、海水が月の引力により引き寄せられ、満潮(水位が最高)が起こります。直角に位置する部分は、海水が引かれるため干潮になり、その影響で反対側でも満潮現象が起こります。月は1日に地球の周りを1周しますから1日に2回/約12時間おきに潮の満ち引きが繰り返されます。これがいわゆる潮汐です。
●日に2回満干潮があるわけですが、同じ満潮(干潮)でも水位の高さが同じとは限りません。たいていどちらかの水位が高くなっています。ある程度、流れの強さは高低差に比例しますから、強い流れの時と弱い流れの時があるわけです。細かい潮見表になると時間だけでなく予測水位も書かれています。「いまが満潮のはずなのに意外と水位が変わらないな」と思うようなときは、水位が低い時の満潮と考えればいいでしょう。
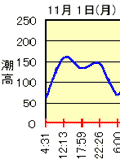 ●右の図はある年の東京芝浦の潮位表ですが、午前中の満干の差が1mあるのに比較して、夜間の満干の差はわずか20cmしかないことがわかります。つまりこの日の夜は、昼ほどは潮が動かなかったということが、グラフから推測できます。
●右の図はある年の東京芝浦の潮位表ですが、午前中の満干の差が1mあるのに比較して、夜間の満干の差はわずか20cmしかないことがわかります。つまりこの日の夜は、昼ほどは潮が動かなかったということが、グラフから推測できます。
●満干潮の時間は毎日変化しています。大体、前日よりも1時間ちょっとずつずれていきます。潮見表にはこの時刻(表によっては水位も)と後述する潮回りが記されており、釣り人の役に立っています。※釣りはともかく潮干狩りには絶対必要!見ておかないと手ぶらで帰る羽目になるよ。
 ●この干満の差を10等分したのが潮時です。よくいわれる「上げ7分下げ3分狙い」などというのは、干潮から70%目の水位と満潮から30%目までの水位を表しています。しかし時計や物差しで正確に測れるようなものではなく、満潮時と干潮時を基準にした相対的なものと覚えておいて下さい。仮に干潮が6時と18時、満潮が12時だとすると、上げ7分は10時すぎ、下げ3分は14時前となります。つまり満潮前後の約4時間弱が勝負というわけです。でも、分かっていても、なかなかその通りにはうまくいかないのですが・・・。
●この干満の差を10等分したのが潮時です。よくいわれる「上げ7分下げ3分狙い」などというのは、干潮から70%目の水位と満潮から30%目までの水位を表しています。しかし時計や物差しで正確に測れるようなものではなく、満潮時と干潮時を基準にした相対的なものと覚えておいて下さい。仮に干潮が6時と18時、満潮が12時だとすると、上げ7分は10時すぎ、下げ3分は14時前となります。つまり満潮前後の約4時間弱が勝負というわけです。でも、分かっていても、なかなかその通りにはうまくいかないのですが・・・。●余談ですが、日常会話でも「いまが潮時〜」とよくいいます。いま現在、いいタイミングだからチャンスを逃がすなということです。昔の帆船はエンジン動力がありませんでした。ですから上げ潮に乗って入港し、下げ潮に乗って出港したのです。けっこう含蓄のある言葉です。
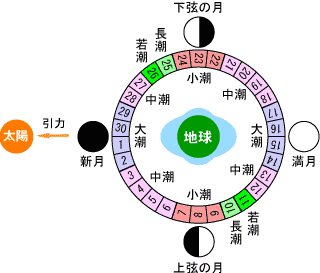 ●お月様は地球の周りを回っていますが、地球も太陽の周囲を回っています。潮汐はこの月と太陽の双方から影響を受けています。これがいわゆる潮回りです。約15日周期で変化しており、月の満ち欠けと関係しています。右図を見て下さい。太陽と月が直列に並ぶときは引力が強まり、海面の上昇が最大になります。逆に直角に位置するときは、引力がうち消される形になり海面の上昇が抑えられます。旧暦(太陰暦)では月の満ち欠け1ローテーション約30日が1ヶ月です。「十五夜お月様」が満月になる理由も分かって頂けましたね。
●お月様は地球の周りを回っていますが、地球も太陽の周囲を回っています。潮汐はこの月と太陽の双方から影響を受けています。これがいわゆる潮回りです。約15日周期で変化しており、月の満ち欠けと関係しています。右図を見て下さい。太陽と月が直列に並ぶときは引力が強まり、海面の上昇が最大になります。逆に直角に位置するときは、引力がうち消される形になり海面の上昇が抑えられます。旧暦(太陰暦)では月の満ち欠け1ローテーション約30日が1ヶ月です。「十五夜お月様」が満月になる理由も分かって頂けましたね。
さて満干の差が大きい潮回りを大潮(おおしお)と呼び、小さくなる潮回りを小潮(こしお)と呼んでいます。その中間を中潮(ちゅうしお)と呼びます。大潮→中潮→小潮と変化しますが、潮が大きくなるときに限って小潮→長潮→若潮→中潮→大潮となります。中潮は「ちゅうしお」「なかしお」どちらで読んでもかまいません。
●潮見表は、この潮回りと毎日の満干潮の時刻を統計学的に予測したものです。あくまでも予測ですから、満干潮の時刻については釣り場によって予測通りにならないこともありますが、潮回りは間違いありません。ちなみに図表の月のシンボルを覚えておいて下さい(○印)。これは月齢を表したものです。闇夜だから●、月夜だから○とでも覚えておけばいいでしょう。潮見表だけでなく、フィッシャーマン用の腕時計などにも使われています。
総体、流れのある方が魚はよく釣れます。活性が上がって餌を摂るからです。ですから潮の動きを読むことは大変大事で、潮の読めない漁師はいません。しかし大潮=潮がよく動く=よく釣れるというほど単純ではありませんし、潮見表そのものにも穴があります。ひとつひとつ検証してきましょう。分かった上で潮見表を使いこなせばよいのです。
 ◆時刻は釣り場で大きく変わる
◆時刻は釣り場で大きく変わる
潮見表には「○○港/○時○分満潮」などと書かれていますが、鵜呑みにしてはいけません。これは海上保安庁がある特定の測定箇所を計った過去の統計的数値です。実際は位置、地形やその年の外洋の影響で大きく変わります。私がよく行く釣り場では約1時間以上、潮見表より遅れます。通い詰めるとその誤差(時間差)が分かってきますから、その分誤差を補正して予測すればいいのです。
◆潮回りを選べる身分になりたい
潮回りは全国的に同じです。ですから行き先を変えても同じです。それに大半のお客様は、お休みの日が決まっているはずです。この日がいい潮回りだと思っても、休んで釣りというわけには行かないはずです。与えられたチャンスで頑張りましょう。
◆潮時は釣り場、釣法、魚種でも変わる
東京湾、とくに観音崎付近では潮がごうごうと流れます。大潮などは川になります。一般的に満干潮時は釣りにならないと云いますが、満干潮時いわゆる潮止まりに入れ食いなんて事も多々あります。潮が大きい時は潮止まりに、潮が小さい時は潮の速い時に食いが良くなる!!!。こんな事もご参考に〜!!!。
◆正確な潮見表が必要
釣具店でくれる潮見表にも色々あります。気をつけておきたいのは関東では東京 芝浦のように代表的な港の満干潮時刻が掲載されていますので、その釣場の時差を加減して下さいね。計算が面倒くさく間違えやすいですが結構時間差がありますヨ〜。また、東京湾、特に久里浜では千葉側から黒潮が入り込むと、1日、底の潮は上げ潮なんていう日もありますので、船長に聞いてください。
釣り場は場所、魚種、季節により大きく個性が異なります。統計的な観測結果でしかない潮見表を見ても、釣果を予測することは困難です。このあまり当てにならない潮見表をどう使いこなせばいいのでしょうか。それはずばり、あなた自身の釣果のデータベースに答えがあります。データベース(=経験の蓄積)がある人には潮見表は力強い見方ですし、ない人には只の紙切れです。
◆まずは潮見表を入手
上にも書きましたが、ある程度の精度のものをまず用意しましょう。海上保安庁水路部が発行しているような大層なものは必要ありません。ポケットに入れられるもので、自分が通う釣り場の潮回りが書かれているものでいいでしょう。遠方へ釣行するなら、その地の釣具店が無料で呉れるはずです。赤鉛筆で釣行日、潮時をマークしておきましょう。釣り場ではよく見間違えるものです。また三喜丸でも年初に無料でお配りしていますし、三喜丸カレンダーにも書いてありますので、ご参考に。
◆必ず釣れるパターンがあるはず、それを見つけろ
私自身は横着者ですから、釣果の記録を取っていません。物覚えも悪い方ですが、勝手なことに、こと遊びに関しては不思議によく記憶しています。釣り場Aは上げ潮が好成績、釣り場Bは潮止まりでよく喰ってくる、Cは潮回りに関係なくぼちぼちアタリが出るとか、大体覚えています。このように釣り場それぞれごとの自分の釣果パターンが読めればしめたもの、潮見表の出番です。そのパターンを潮見表に当てはめればいいのです。
たとえば「この釣り場では大潮の下げで何回もいい釣りをしている」と分かれば、その潮回りと潮時を選ぶのです。希望的観測は往々にして外れますが、統計的推測は釣れる確率をある程度保証してくれます。実際、そのように実践して成功している釣り師もたくさんいます。潮時の誤差が分かるようでしたら、時刻を補正しておきましょう。より釣行時刻の目安が立てやすくなります。
◆釣果と潮回り、潮時を記録しておくのが一番
「いま、あなたが大物を釣ったとします。来年の同じその日、同じ釣り場、同じ潮回り、同じ潮時に、また大物が釣れるはずです。ただし太陽暦でなく太陰暦(いわゆる旧暦=月の運行による暦)で日付を記録しておかなければいけません」
これは昔聞き及んだ名人の話ですが、真偽はともかくなるほどと頷けるものがありますので、ご参考までに書いてみました。もっとも始めからデータベースは誰にせよありませんから、やはり潮見表を見つつ相関的なデータを積み立てて行く必要があります。初心者でも潮見表を見ることは、決して無駄ではなく将来役立ちます。
◆潮見表を忘れたときは
 港の防波堤を見れば簡単です。カラスガイが隠れているようなら満潮時ですし、大きく見えているようなら干潮です。中間の潮時はカラスガイの見え加減で判断します。夜釣りなら空を見て下さい。満月あるいは新月でしたら大潮です。ちょうど半弦の月なら小潮、欠けた月や三日月なら中潮です。月が水平線なら干潮ですからこれから潮が満ち始めますし、真上に輝いていたら、いままさに満潮を迎えようとしています。私は横着者ですので、「あっ、潮見表忘れた〜、お客さんちょっと貸して〜」なんて、ほとんど済ませています。解説者としてお恥ずかしいかぎりです(^^;)
港の防波堤を見れば簡単です。カラスガイが隠れているようなら満潮時ですし、大きく見えているようなら干潮です。中間の潮時はカラスガイの見え加減で判断します。夜釣りなら空を見て下さい。満月あるいは新月でしたら大潮です。ちょうど半弦の月なら小潮、欠けた月や三日月なら中潮です。月が水平線なら干潮ですからこれから潮が満ち始めますし、真上に輝いていたら、いままさに満潮を迎えようとしています。私は横着者ですので、「あっ、潮見表忘れた〜、お客さんちょっと貸して〜」なんて、ほとんど済ませています。解説者としてお恥ずかしいかぎりです(^^;)
さて、これから始める人やアベレージ釣り師でしたら「データベース?それがあったら苦労せんわ!」と怒られそうです。では私自身の独断ですが、参考になるようなインスタント潮見を書いてみます。その通りに行かなくても怒ったらあかんよ〜
◆上げ7分下げ3分というが…
時合いを評して、満潮前後がよく潮止まりは喰わないといいます。確かに湾内ではべたべたの潮止まりは食ってこないものです。しかし本流筋(海峡や外界に面したところ)では一見動いていないように見えても、じわりと底潮が動いているものです。注意深く観察しているとわかるのですが…。こんな時は気を抜いてはいけません。セオリーだけに縛られないように〜。
◆むしろ上げっぱな、下げっぱなに集中しろ
経験的にいえることですが、潮が止まっていたときから動き出すときにアタリが連続することが多いものです。これは多くのお客様が認めるところです。静止したときから動くときに一気に魚の活性が上がったるのでしょうね。例え話ですが、久里浜や観音崎でのアジ釣りの時に、上げ止りから下げに入るときにアタリが集中しました。そのことをお客様に云うと「うん、ここは前回も下げっぱなが良かった」という明快な返事でした。こうなると潮見表が役に立ってきます。数字を見ながら次回の釣行予定日を考えるようになります。
◆経験的にはやはり大潮〜中潮か
あまり潮回りを気にしないですが、東京港ではここは、大潮の方が成績が良い、ここでは、小潮回りの方が良いと場所によってマチマチです。場所によっては大潮でもとろかったり、小潮でもよく流れる日があり、奥が深いというか、よく分からない時も多いのですが…。私自身の記憶でも久里浜で若潮でタイがバリバリたったり。潮見表で長潮などと書かれているとげっそりしますが結構釣れちゃうときもあります。いまだ理由は不明ですが、意見を同じくする船長も結構多いようです。流れにメリハリがなく、だらだら流れるだけだからという説もありますが…。
◆潮見表を鵜呑みにするな
前出しましたが、潮見表の時刻はある測定地点を元にした推定ですので、場所によって1時間ぐらい変動することはざらです。よく通う釣り場の潮の遅れは頭に入れておくことです。通うと分かるようになります。マニュアル人間の方は、どうも潮見表を頭から鵜呑みにするようです。総体的には、岬周りや島周りは潮が良く通したり、おくの深い湾内ほど遅かったりと様々ですね。
◆外洋に面したところでは
前回に書きましたが、久里浜沖や剣崎沖、館山沖では、潮汐よりむしろ外洋の流れ(地球の自転から生まれる)の影響を受けます。千葉側は太平洋に面していますから、黒潮の影響がもろです。黒潮が接岸して洲崎に当たると分岐して上り潮(千葉方面から観音崎に流れる潮)と下り潮(久里浜方面から城ヶ島に流れる潮)に分かれます。年によってこの流れはずいぶん変りますし、釣り場によっても上り下りの善し悪しがあります。この方面に出かける方は覚えておいて下さい。
◆太平洋側では大潮の後の中潮に注意
太平洋側では「大潮の後の中潮がいい」といわれます。理由は朝夕のマズメ時が満潮とうまく重なるからです。ということは一日に2回チャンスがあります。これは相当美味しい話です。太平洋岸の方はぜひ覚えておいて下さい。
◆干潮時に喰わないもう一つの理由
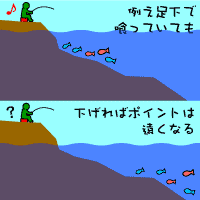 干潮時には総体的に釣れないものですから、ベテランの中にはさっさと昼寝をかます人もいます。これも潮時を待つテクニックの一つです。しかしそれだけではありません。沖から手前へ駆け上がりになったような釣り場では、水位が低くなるにつれポイントが足下からどんどん遠ざかります。こういうときはかなり沖目を釣る工夫が必要です。逆に潮が満ちてくるとポイントが近くなってきます(河口では満ち潮に乗って魚が上ってきます)。人があきらめるような干潮時でも、しつこく釣りを続ける当道場の読者ならば、覚えておかなければいけない摂理です(^^)
干潮時には総体的に釣れないものですから、ベテランの中にはさっさと昼寝をかます人もいます。これも潮時を待つテクニックの一つです。しかしそれだけではありません。沖から手前へ駆け上がりになったような釣り場では、水位が低くなるにつれポイントが足下からどんどん遠ざかります。こういうときはかなり沖目を釣る工夫が必要です。逆に潮が満ちてくるとポイントが近くなってきます(河口では満ち潮に乗って魚が上ってきます)。人があきらめるような干潮時でも、しつこく釣りを続ける当道場の読者ならば、覚えておかなければいけない摂理です(^^)
必ずしも潮汐とは関係のない話ですが、いっぱしの釣り師を目指すあなたのために、ちょっと参考になるお話を書いておきましょう。
◆潮より技の問題?
釣りをしているとき、潮が流れているときは全く釣れず、止まったらぽつぽつ喰ってきたという経験のある方もおられるでしょう。もちろんそういう潮時の時もありますが、これには技術的なことも絡んでいます。初心者の方だと、仕掛けが流れで浮いてしまってタナが取れていないとか多々あります。流れが弱まると仕掛けがポイントに入り、タナも正確に取れますから、魚さえいれば食って来るという構図です。いい潮だったとは必ずしもいいきれませんね。
◆冬に南や西の風が吹くと
一般的に水温が下がり、スミイカ釣りにはいいと云われています。もっとも釣り場の位置や地形で変わりますが、水温が下がって、イカが固まると云われています。また、ムギイカなどはシケ後は大爆発〜、何てこともありますので、気を付けて〜!!!
 ◆日の出日の入り
◆日の出日の入り
他の章でも再三取り上げていますが、潮時と並んで朝マズメ、夕マズメは釣りのゴールデンタイムです。ですから日の出日の入りの時刻を知っておくことは、釣り師の基本的な心構えです。新聞の天気予報欄を見ても分かりますし、インターネットの予報なら潮回りも含めて知ることができます。
◆かくいう船長はどうなのか
この潮はたくさん釣れた、あの潮は全然釣れなかった、なんと良く云いますが、結局は船長が良い釣り場に入り、お客様ががんばって釣って頂かなければ、釣果は上がりません。どこの船長も、置きゃさまに1尾でも多く釣って頂こうとがんばっています。でも日によって全然釣れなかったり、それを、潮もせいにする事も多々ありますが、みんながんばっているので、多めに見て下さいね。次回きっと大釣りさせてくれるでしょうから。でも、あまり予備調査をすると気合いが入りすぎて殺気が魚に伝わるのでしょうか、準備万端の日ほど貧果です。こりゃ参考にならんないかな(^^;)
![]()
天文学はよぅわからん
本章ではとりあえず、釣りに関係するような潮汐のお話をまとめてみましたが、一年で一番大きい潮の日があるなど、ニュートンの法則はまだまだ面白い潮汐現象を生んでいます。私の浅学では、残念ながらその全てをお伝えすることができません。興味がおありでしたら、専門書でじっくり研究してみて下さい。